<連載 第2弾> 現代の日米の大学をめぐる見解【第2回】学問の自由、大学の自治について
1. 学問の自由・大学の自治の起源と文脈
◉ ドイツ型モデル(19世紀末)
• 起源:学問の自由(Freiheit der Wissenschaft)と教育の自由(Lehrfreiheit)は、19世紀のドイツ(特にフンボルト大学)で理想化された概念
• 意義:国家からの独立と、教授・研究・学生の自律的空間の保障
• 限界:この「理想」は帝政下・ナチス時代に破綻しており、実際には政治的制約が常に存在していた。
◉ 米国型モデル(20世紀)
• 発展:1940年にAAUP(全米大学教授協会)が採択した「学問の自由と任期制度に関する声明」が米国大学のスタンダードになる
• 現実:冷戦期のマッカーシズムや、9.11後の愛国法(Patriot Act)など、国家の安全保障が優先される場面で幾度も制限されてきた。
2. 現代における大学の自治とその限界
グローバル視点での比較

<自治の限界の背景>
• 財政依存:多くの大学が国家補助金や研究費に依存。資金の引き締めが即自治の制限に。
• 安全保障の優先:国家安全保障(特にAI、量子、バイオ分野)と研究の自由が衝突。
• 政治的文脈:国家アイデンティティ、宗教、民族などの課題が学問と交差。
3.大学の新たな「自治」の構築に向けた動き
デリック・ボクの「大学は社会から恩恵を受ける存在であり、社会への責任がある」という思想は、大学が閉じられた聖域であるという考えに一石を投じた重要な指摘になる。
大学の自治への問い直しについて:
• 「自治」は自己目的ではなく、社会との対話によって成立。
• 説明責任(accountability)と公共性(public engagement)の重視。
• 「自由な学問」は、その成果が公共財となることで初めて正当性を持つ。
4. 代替的価値観やモデルは存在するか
• 開放的制度自治(Open Institutional Autonomy):
o 政府と距離を取りつつも、公共政策と接続する「協働型の自治」
o 例:欧州の「Civic University」モデル(市民社会との連携重視)
• 領域別ガバナンス:
o 国防・経済安全保障に関わる領域は国の規制下、他は自律という「二層モデル」。
o 例:イスラエルの技術系大学では軍事研究と市民的研究の制度的切り分けが進む。
5. 示唆するもの
• 米国の大学自治も絶対的なものではなく、政治・経済・安全保障の状況次第で揺らぐ構造的脆弱性を抱えている。
• トランプ政権の動きは、ある意味でその構造的限界を露呈したものであり、「自治」の再定義を促しているとも言える。
• 日本の大学・政策関係者も、「学問の自由」と「国家の要請」とのあいだで、理念と現実を調整する新たなフレームづくりが求められている。
参考資料
【1】米国における「学術的正当性(academic legitimacy)」の意味
米国で学術的正当性とは、以下の複合的な評価基準:
| 評価基準 | 内容 | 例 |
| ピアレビュー制度 | 学術論文・研究予算の採択において、専門家集団による厳密な相互評価 | NSF、NIH、DOEの競争的研究資金 |
| 研究倫理と独立性 | 政治的・経済的な圧力からの相対的自立 | 政権批判も許容される大学の自由な言論環境 |
| 制度的透明性 | 研究・資金・人事に関する運用ルールの公開性 | IRB(倫理審査)制度、Tenure(終身在職権)の公開プロセス |
| 社会的信頼性 | 公的資金の適正使用と市民への説明責任 | 大学が地域経済・教育・医療・技術革新に貢献しているという実績 |
| 多様性・開放性 | 多様な背景を持つ研究者・学生の受け入れと議論の包摂性 | ファーストジェネレーション大学生支援、多文化キャンパス推進 |
したがい、米国では「政府と対立しても制度的・社会的に支持されている大学群」は、依然としてacademic legitimacyを強く維持しうる(例:ハーバード、MIT、スタンフォードなど)。
【2】日本学術会議の「正当性」との違い
日本学術会議は、以下のような要素で「学問の代表機関」としての正当性を主張してきた:
• 科学者による推薦制度(=自己充足的な選考プロセス)
• 法律に基づく内閣府所管の「日本学術会議法」
• 政策提言機関としての独占的地位
しかしこの正当性は、米国における学術的正当性とはいくつかの点で大きく異なる
| 項目 | 日本学術会議 | 米国の大学・学術機関 |
| 構成・選出 | 自己推薦・互選による固定的人材構成 | 開かれた公募、競争評価制度 |
| 政治からの独立性 | 制度的には内閣府の所管(=政治からの距離不明確) | ガバナンスは理事会・評議会による自主性が原則 |
| 評価・説明責任 | 外部からの査定・予算検証の制度が曖昧 | 監査、公表義務、第三者評価が常態化 |
| 社会との関係 | 政策提言の実効性に乏しい例が多い | 地域連携・企業連携・NPOとの協働による信頼形成 |
つまり、日本学術会議の正当性は閉鎖的自己制度に基づく“自律”の主張に偏りがちであり、「社会的信頼・説明責任・多様性」という視点が決定的に欠如
【3】今後の日本にとっての示唆
• 米国のacademic legitimacyは、政治権力からの独立と、社会との実効的な関係性の両立によって成り立っている。つまり「反権力」だけでも「専門性」だけでもなく、「開放性×説明責任」が求められる。
• 日本の大学や学術機関は、社会に開かれたガバナンスと多様な声を受け止める包摂性を高めなければ、真の「正当性」を持つ知の担い手としての信頼を失っていく危険があろう。

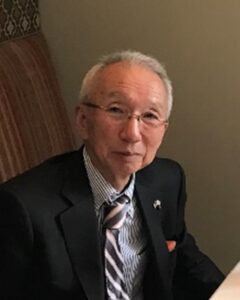
-1-300x169.jpg)