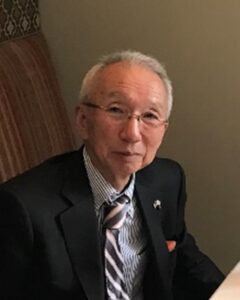<連載第2回>日米デジハブ立ち上げの経緯
安倍政権が再稼働を試みた日米の「知」の交流
日米デジハブにはルーツがある。2013年4月30日(午後)ワシントンDCのカーネギー国際平和基金(CEIP)で開かれた公開フォーラム“Science and Technology to Promote Economic Growth: U.S.–Japan Public-Private Forum”(以下、オープン・フォーラム)、これは米国務省とCEIPが共催し、日米両国の政府高官、大学、シンクタンク、産業界の代表が一堂に会した公開イベントだった。同日午前に国務省で「第12回日米科学技術協力合同高級委員会(JHLC)」が開催されており、その議論の内容を産業界・学界・市民に届けることを目的として実施された。
JHLCは1988年のレーガン・竹下会談で締結された日米科学技術協力協定に基づき設置されたもので、両国のトップが科学技術協力を議論する司令塔的役割を担う。その下に専門家レベルの「日米科学技術連携実務合同委員会(JWLC)」が置かれ、JHLCの議論の整理や新たな議題設定、日程調整を行っている。しかし体制は整っているものの、議論が産業界や学界・市民に広がりにくい、いわゆる縦割りの弊害「ストーブパイプ」現象がある。これは、ストーブの煙が部屋に広がらずパイプで外へ排出される仕組みにたとえられ、重要な議論が必要な関係者に届かないという問題を指摘している。
安倍政権と科学技術交流再始動
2012年末に発足した第二次安倍政権は、「経済成長で日本を取り戻す」というフレーズを全面に掲げた。これを支える科学技術と教育(人材づくり)での国際交流、とりわけ米国との交流を再活性化させる方針も打ち出した。日本の発展は明治維新期のみならず戦後復興期にも米国との交流が大きく寄与してきたが、バブル崩壊後の長い停滞の中でその重要性は忘れられがちとなり、いわゆる「ガラパゴス化」が進んでいた。なお、日米交流の大切さは米国にとっても同様である。(次回の連載では、この点について述べたい。)
米国務省で開かれた第12回JHLCには、米側はホルドレンOSTP(ホワイトハウス科学技術政策局)局長(大統領科学技術補佐官)とコルグライザー国務省科学技術顧問、日本側は、山本科学技術政策担当大臣と下村文部科学大臣等が参加した。日本側には、これを機に科学技術・教育で日米の本格的な交流を推進したいという強い意欲があった。私も文部科学省の「参与」として参加した。大学人として他省庁の政府委員を務めた経験があったが、文科省からの打診は初めてのこと。しかし当時の文科省トップは、私が米側高官等と交流があることを知っており、参与の就任を求められた。私に課された当面の役割は、外務省と連携し米側との調整を行うことだった。
オープン・フォーラムの試み
外務省に「JHLCの後に公開フォーラムを共催したい」と米側から申し入れがあり、文科省の見解を求められた。私は長い付き合いのあるコルグライザー氏に連絡を取った。コルグライザー氏は、「JHLCの議論だけでは産業界・学界・市民社会に十分に広まらない懸念がある。民間を交えた公開の場を設けてはどうかという案が国務省内で出ている。欧州ともまだ実施していないが、まず日本とやってみたい」と述べた。米側も「ストーブパイプ」現象の改善を考えていることが分かり、私は外務省に受諾を促し、「日本側の登壇者探しは文科省でも支援できると思う」と伝えた。具体的な目安があったわけではないが、日立・日産の執行役員、京都大学の副学長が登壇に応じてくれた。午前中のJHLCに続き、車で10分ほどのCEIP会場に移り、第1回オープン・フォーラムが開催された。タイトルは日本側の希望も反映して、“経済成長促進のための科学と技術”になり、人的資源開発・研究者交流、先端材料の共同開発など日米の経済成長に関わるテーマが中心となった。また、東日本大震災の復旧で注目された「災害時のビッグデータと高性能コンピューティングの応用」も取り上げられた。米国務省とCEIPの強い後押しもあり、フォーラムは大きな反響を呼んだ。
日本での継続 (第2回オープン・フォーラム)
2014年7月7日に東京でJWLCが開催され、米国務省科学技術協力局長ハスケル氏の来日が決まった。私は外務省に実務委員会の機会をとらえ、第2回オープン・フォーラムを共同開催してはどうかと提案。米国務省も賛同し、文科省は外務省と組んで準備を進めた。開催はJWLCの開催日の翌日にお台場の日本科学未来館に決まり、テーマのタイトルは“新しい社会への進化—科学的知見とイノベーションの活用”になった。当時、米側はハスケル局長、ケネデイ駐日米大使、日本側は、外務政務官の岸氏、iPS研究の京都大学・山中教授、清水建設の宮本会長等が登壇し、岸氏が安倍総理の「日本のイノベーション力を高める決意」を代読した。多くの聴衆が集まり、活発な質疑が行われた。
第13回JHLCと第3回オープン・フォーラム
2015年は第13回JHLCが4月にワシントンDCで、10月に東京で開かれるという変則的な形となった。
4月26日〜5月3日、安倍総理が日本の総理として初の米国国賓として訪米し、オバマ大統領との首脳会談、米議会上下両院合同会議で演説を行った。4月30日には米国の知の殿堂NAS(米科学アカデミー)本部でSTSフォーラム共催の朝食会に出席し、シセローネNAS総裁らと協力について意見交換を行った。日本の総理がこのような機会を持つことは、長い日米の歴史の中で初の出来事であった。同日、国務省で第13回JHLCが開かれ、バイオ、データ、スーパーコンピューティング、エネルギー分野での戦略協力が議論された。
10月には東京で再度JHLCの会合が開かれることになり、ホルドレン氏や国務省科学技術顧問トレキアン氏の来日が決定。会合後、三田共用会議所で第3回オープン・フォーラムが開催された。共同議長はホルドレン氏、山口科学技術政策担当大臣、下村文部科学大臣。コルグライザー氏は不参加であったが米側関係者への働きかけを行い、米科学誌『Science』の編集長、NSF(米国立科学財団)国際科学局長、ムーディーズ会長等が参加。日本側からも理化学研究所の松本理事長、JST、NEDOのトップ等が参加した。テーマは、“日米科学技術協力の将来―世界の人々に豊かな生活をもたらすための科学の発展と日米の果たすべき役割”であった。
日米デジタルハブへ
オープン・フォーラムはJHLCの「ストーブパイプ」の改善には役立つと私は確信した。しかし日米科学技術協力を進めるためには、さらに大きな課題があった。第3回オープン・フォーラムの案内には、“急激に新興技術が発展する中で、日米関係者が科学技術協力の在り方を議論する”と記したが、大きな課題とは、急速に発展するこれら新興技術分野で日米協力を如何に有効に行えるか、であった。
当時、この新興技術とは、「デジタルテクノロジー」、「アドバンストテクノロジー」と呼ばれていた(現在ではCET、重要・新興技術と呼ばれている)。 これらの多くは、当初米国のシリコンバレーを中心に急速に発展したが、その背後には2010年代に顕在化した「ニューサイエンス」の伸長があった。 QIS(量子情報科学)は、「重ね合わせ」や「エンタングルメント」を工学的に操作する“量子第二期”に入り、同時期にLLM(大規模言語モデル)を含むFMS(基盤モデル科学)も急伸した。これらのニューサイエンスがAI・データサイエンス・量子コンピュータ・半導体など一群のCETの発展を加速させだした。また、CET同士で相互に発展を促し合うことも起きている。たとえばAIの進歩がデータサイエンスや量子計算、半導体の発展を押し上げ、それがまたAIを前進させるという循環が生まれている。こうしたCETの発展には、従来の政府組織だけでは対応しきれない。事実、2010年代半ばには、米国防総省は動向を把握するためにシリコンバレーに常駐事務所を設け、調達でも規則は守りつつ、手続きを軽くする簡素化:lightweight frameworkを立ち上げている。さらにグーグルの会長だったシュミット氏ら外部専門家を招いた諮問委員会を設置している。つまり、急速に発展する新興技術に対するオープン・フォーラムはあるのか。ただ、この問いかけは、日本だけでいくら考えても答えが出ない。幸い、私は30年以上交流を続けてきた米ビジネス高等教育フォーラム(BHEF)の関係者を通じて、米国の産学トップの考えを聞くことができた。なお、BHEFは米国を代表する大学と産業界のトップが個人資格で参加し、産学の在り方を議論するフォーラムである。
これらで得た答えは明快だった。日米の政府、産業、大学・研究機関が協力に関する話し合いを持つ場を有志の間で構築する、である。いわば、自主的に動くオープン・フォーラムへの衣替えであった。そして、当初の名は、「日米デジタルイノベーション・ハブ」とした。この後、日米の大学・研究機関、駐米日本大使館、外務省、文科省、経産省、NEDO、JST、理化学研究所等、そして産業界の賛同を得て、2015年11月に、ワシントンDCのコスモスクラブ(Cosmos Club)において第1回の会合が開催された。コスモスクラブは1878年創設でノーベル賞受賞者をはじめ米政府要人や各界リーダーが多数所属している。歴代大統領経験者が名を連ねた時期もあり、知的交流と公共奉仕を旨とする「知の社交場」である。
なお、ここまで一人称的に記したが、決して私が中心だったということではなく、当初から議論と実務に参画した一人であったことを記しておきたい。オープン・フォーラムから「日米デジタルイノベーション・ハブ」に至るまで、いかに日米交流の強化を重視する多くの方々と出会えたかを痛感している。
次回(第3回)では、なぜ日米交流が不可欠なのか―ハブが目指した必然を述べたい。