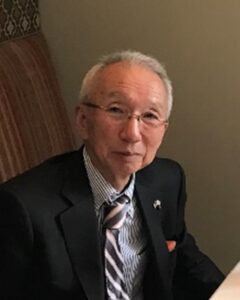トランプ関税を超えて:アメリカ発の新たな時代への動き
トランプ2.0政権の発足から7カ月。世界はいまだにトランプ大統領の高関税政策で揺れ続けている。日本も例外ではなく、その対応に苦慮してきた。しかし、これは単なる通商政策の一断面にとどまらず、戦後体制の根幹に関わる変化の兆しかもしれない。
私が抱いている仮説はこうである。
トランプ大統領は、第二次世界大戦後に米国が世界に広めた「アメリカ式リベラリズム(自由主義体制)」の行き過ぎがもたらした弊害を是正しようとしているのではないか。 この文脈でみると、トランプ高関税政策は、アメリカと世界との関係を再構築しようとするトランプ大統領の決意と位置づけられる。
では、「アメリカ式リベラリズム(自由主義体制)」とそれがアメリカにもたらした「行き過ぎ」とは何か。
ノートルダム大学のデニーン教授は、著書『なぜアメリカ式リベラリズムは失敗したか』の中で、リベラリズムを ①徹底した個人主義、②文化的リベラリズム(価値観やライフスタイルの多様性の擁護)、③市場至上主義、④グローバル化の推進、⑤小さな政府、にあるとした。
個人主義の行き過ぎはアメリカ本来の家族・地域共同体を喪失させた。また、文化的リベラリズムの行き過ぎがもたらす多様性の擁護もアメリカ社会の分断と争いを拡大させた。例えば、少数派への差別解消を目的に導入されたDEI(多様性・公平性・包摂)の過度な推進は、多数派への不公平感を生み出す要因となった。
市場至上主義とグローバル化の推進の行き過ぎは富の偏在を生み、本来のアメリカの強みであった中産階級と製造業を没落させた。さらに小さな政府路線の推進しすぎは産業政策を放棄させ、レアアース(希土類)などサプライチェーン等、経済安全保障に多くの問題がもたらした。このように捉えると、トランプ政権の高関税政策は、「アメリカ式リベラリズムを超える新たな体制」への移行を促す手段の一つと理解できる。
実はこの「行き過ぎ」がもたらした弊害はアメリカに限らず、日本や欧州を含む西側諸国でも深刻化している。とりわけ日本は、アジアの中で最も徹底してアメリカ型を導入してきたため、家族・地域共同体の希薄化、産業空洞化、富の偏在といった形で強い影響を受けてきた。もちろん、日本はトランプ関税には毅然とした交渉で臨み、国益を守る必要がある。ただ、それだけでは、真に国益を守るとは言えない。そのためには、日本を再び強くする戦略が必要になる。
そうした背景を踏まえ、私たちは今、トランプ高関税政策の背後にあるアメリカが踏み込もうとする新たな時代への変化を見据えつつ、日米が未来志向で技術・人材・価値観の協力をどのように再設計できるか、を問い直すべき段階に来ている。
私はこの問題意識のもとに、大学・企業・政府の連携を通じて、新たな協力の枠組みを構築する試みを支援し続けてきた。 その一つが7月20日に上智大学で開催された「第9回 日米デジタルイノベーション&アドバンストテクノロジー・ハブ(以下、日米デジハブ)」である。これは、日米の有志たち(大学トップ、産業界の戦略責任者、政府の政策担当者)が一堂に会し、先端技術の社会実装とルール形成を協議する場である。https://air.tsukuba.ac.jp/workshop2025/
次回から5回に分けて、この日米デジハブについての全体像を紹介したい。なぜこうした場が生まれたのか。どのような問題意識のもとに進めてきたのか。そして今後、日本がいかに新たな時代に向け、米国、また他の国々との協力体制を進めていくのか。これについても一部立ち入るつもりである。

-1-300x169.jpg)