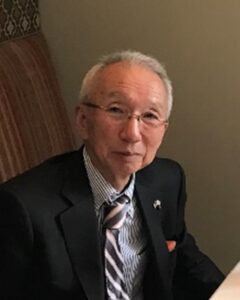<連載 第2弾> 現代の日米の大学をめぐる見解【第1回】大学と社会の関わりについて
トランプ政権2.0下では、ハーバード大学をはじめとするアイビーリーグ校との対立が一層顕著になっている。2023年秋の中東紛争(イスラエルによるガザ侵攻)を契機に、ハーバード大学やコロンビア大学では反イスラエル的な言動や、反ユダヤ主義と受け取られる発言・運動が激化し、これが米社会に深刻な分断と混乱をもたらした。議会での公聴会を経て、アイビーリーグの複数の大学学長が辞任に追い込まれる事態となった。
トランプ大統領は、一部の大学を過度にリベラルな思想やDEI(多様性・公平性・包括性)政策の拠点と見なし、「治外法権化した組織」として公然と圧力をかけている。こうした動きが示すのは、大学の自治とその社会的責任の在り方が、今まさに問い直されているということである。
この機会に、現代の大学とは何かという根本的な問いに立ち返りたい。以下に、私自身がかつて深く感銘を受けた、ある米国大学長による大学の役割に関する問いかけを紹介する。
大学の役割について (ボク学長の「大学自治の再構築」への問いかけ)
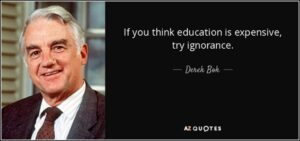
デリック・ボク(Derek Bok)元ハーバード大学学長:
ボク氏は20年間にわたりハーバード大学の学長を務め、さらに2000年代に同大学が混乱に直面した際には再び学長に就任し、政治学者として多角的な視点から大学の在り方を問い続けてきた人物である。
筆者(武田)が参加していた米国の産学フォーラム(BHEF: Business-Higher Education Forum)の1990年冬季会合において、ボク学長は「産業界も大学も社会の一員であり、それぞれの役割の中で協働し、社会に貢献する必要がある」との見解を述べ、産学連携の重要性を強調した。
とりわけ印象に残っているのは、彼の次の言葉である。
“I think any self-respecting educational institution ought to judge its policies by its best estimate of what their long-term consequences for their students and for the society will be.”
すなわち、「真に責任ある教育機関であれば、自らの教育方針が学生の将来、ひいては社会全体にどのような長期的影響を及ぼすかを慎重に見極め、その上で判断を下すべきである」という趣旨である(意訳)。
ボク氏の根本的な問いかけ――「大学は社会から恩恵を受ける存在である以上、社会に対して責任を果たす義務がある」という考えは、大学を“閉ざされた聖域”とみなす従来の発想に一石を投じたものである。
彼は、大学は単に知識を伝える場ではなく、社会の一員としての責任を担い、その教育方針や活動が学生と社会に与える長期的影響を見据えながら行動すべきだとする、きわめて現代的かつ実践的な大学像を提示している。
◎ 現代の大学への問い直し
- 「大学の自治」は自己目的ではなく、社会との対話と信頼の中で初めて成立する。
- 説明責任(accountability)と公共性(public engagement)の確保は、現代大学の基本的要件である。
- 「自由な学問」は、その成果が社会全体の共有財(公共財)として機能するときにこそ、その正当性と価値が認められる。