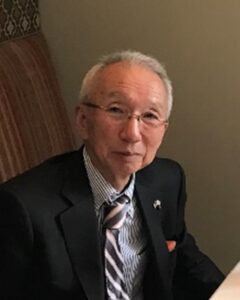<新連載第1回>プロローグ編 ~ 新しい日米協力の時代へ:日米デジタルイノベーション&アドバンストテクノロジー・ハブ(U.S.-Japan Digital Innovation & Advanced Technology Hub)について
日米デジタルイノベーション&アドバンストテクノロジー・ハブ(U.S.-Japan Digital Innovation & Advanced Technology Hub、(以下:日米デジハブ)は、「第三の柱」となり得るか。
世界の潮流と日米デジタルハブの位置づけ
世界は今、トランプ大統領がもたらした高関税政策による混乱に直面しているように見える。
しかしその背後には、「新たな世界秩序の形成へ向けた大きなうねり」があると私は捉えている。このうねりは2010年代に入り本格化し、アメリカ・中国・欧州等諸国で次の時代の繁栄を約束する先端技術(CET:Critical & Emerging Technologies)を軸に、国家戦略としての資産化やルール設計の再構築が始まっていた。こうした状況を背景に、日本の有志(大学・産業界・政府)関係者は2015年以来、米国側有志の関係者と連携し、双方に組織委員会を結成して日米デジハブのワークショップを継続的に開催してきた経緯がある。
日米デジハブの主役者たち
「日米デジハブ」について、ほとんどの人は知らないと思うので若干の説明をすると、これはいわゆる学術研究の発表会ではない。ここに集うのは、大学のトップ、政府、産業界のデジタル分野の責任者である。もちろんAIや半導体のトップ研究者たちも一緒に参加するが、主役は「技術を社会に実装し、制度や仕組みを動かす立場の人々」である。つまり日米デジハブは、日米が協力して未来社会の“実装設計図”を描く場であり、私はこれを共創空間とも呼んでいる。
ボランティアの知的同盟
日米デジハブは2015年、ワシントンDCで第1回ワークショップを開催、スタートした。以来、両国の有志関係者が草の根で繋がり、日米交互にワークショップを重ねてきた。特別な政府予算や制度に依拠するものではなく、双方の組織委員会とプログラム委員会が手弁当で立ち上げたボランティアによる知的同盟である。2020年のコロナ禍で一時中断したが、2022年の秋に米大学側からの強い要望により、少人数ではあったがワシントンDCで再開した。ただ、これは番外のワークショップで、2023年に復活した第7回は、「G7デジタル大臣による会合」と並行して高崎で開催し、第8回は2024年にオハイオ州コロンバスで開かれた日本・米国中西部会合後につなげて、オハイオ州立大学が主催で開催することになった(なお、この部会は日米経済協議会が主催し、イリノイ、カンザス、ミシガン、オハイオなど米国中西部の11州知事と日本の関係者が集まり、関係強化を図る会合)。そして本年、年7月20日に上智大学主催で第9回会合が開催された。
日米政府関係が不透明な中で機能した共創空間
第9回会合の7月20日は日曜日で、しかも参議院選挙とも重なった。また、日米関税交渉はこの段階でも予測がつかず、不透明な状態が続いていた。それが影響したのか、出席予定の米政府関係者は直前で欠席となった。しかし、ワークショップには熱気があふれていた。米国7大学から15名の幹部、日本からは7大学の学長・副学長が集結。外務省・経産省・文科省・内閣府、産総研やJAXAの責任者、さらにラピダスや東京エレクトロン、清水建設など産業界の代表も出席し、総勢100名を超える方々が休日を返上して参加された。また、昼食時には大学院生によるポスター発表も行われ、未来を担う若い世代がワークショップを盛り上げた。
会合の論点は4つ:未来に直結する議題
主催側の上智大学杉村学長による開会宣言の後、日本側組織委員長である筑波大学の永田学長が今回のワークショップでの4つの論点を提示した。
1. 半導体やAIなど先端技術で日米がどう共創体制を築くか
2. 経済安全保障と研究の自由をどう両立させるか
3. 政治と技術が一体化する時代に大学や産業界はどう責任を果たすか
4. 新しい時代にふさわしい日米関係をどう再定義するか
一見すると抽象的な論点であるが、これらはいずれも私たちの日常生活に直結するものである。たとえば、半導体供給の停滞はDXを止め、AIの不透明さは自由な言論を脅かす。私たちの安全・自由・利便性をどう守るか――それこそが議題の核心であった。
会合の総括と未来への布石
会合は夕方6時まで議論が続いた。私はクロージング・リマークの一人として担当したが、その中でこう述べた。「本日のワークショップは、単なる情報交換ではない。日米の大学・政府・産業界が、より効果的かつ緊密に連携するための確かな枠組みづくりを行う場であった」と。この後、上智大学のファカルティクラブでネットワーク・レセプションが開かれ、多くの参加者が残り、枠組み作りの話が続いた。来年の第10回ワークショップは、米国パデュー大学で開催されることが決まった。日米デジハブは次のステージへ動き出している。
「第三の柱」へ
日米デジハブは、対外的なマスコミへのアピール度は決して高くない。しかし関係者たちは、たとえ誰がホワイトハウスのトップであれ、あるいは官邸の主が誰であれ、粛々と次の時代への連携・協力の枠づくりを行うべきであるとしている。日米デジハブが「第三の柱」となり得るのではないかと考えだすものもいる。果たして、第三の柱に本当になり得るのか?ブログを通じて、このプロローグを皮切りに5回連載で日米デジハブの全体像を紹介したい。次回は、日米デジハブがどのように生まれ、なぜ必要とされたのか――その「立ち上げの経緯」を振り返える。
~連載テーマ~
1. プロローグ:新しい日米協力の時代へ(本稿)
2. 立ち上げの経緯:なぜデジハブが始まったのか
3. なぜ必要か:変革期における問題意識
4. 議論の現場:第9回ワークショップ会合の熱気と論点
5. 未来と展望:日米協力の戦略的意義
参考:
日米デジハブ第9回のリンクhttps://air.tsukuba.ac.jp/workshop2025/#program