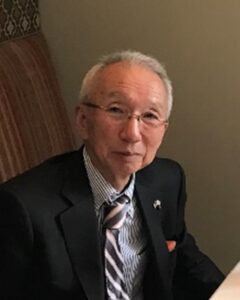【AMが切り拓く未来の製造業についてー AM:Additive Manufacturing(3Dプリンター)】第73回無名塾(7月10日開催) 講師:前川 篤 氏 (大阪大学招聘教授/静岡理工科大学 総合技術研究所 客員教授)
<講師略歴>
2013年~2020年 三菱重工業(株)取締役副社長 エネルギー・環境ドメイン長
2014年~2021年 TRAFAM理事長(Technology Research Association for Additive Manufacturing)
2020~2025年 京都大学 大学院思修館 特任教授 2016~2025年 AMRFC(オール三菱ラグビーフットボール倶楽部)会長
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<塾僕武田より~松本紘先生のご逝去について>
無名塾のファウンディングメンバーのお一人であった 松本 紘先生(京都大学総長、理化学研究所理事長、国際高等研究所所長など歴任)が6月15日にご逝去された。先生には、無名塾で大学のあり方やリーダーシップについて何度も熱いお話をいただいた。本当に惜しい方を亡くしたと思う。謹んで先生のご冥福をお祈り申し上げたい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
<前川篤先生のご講演について>
AM(積層造形)はご承知の通り、当初3次元プリンティングと呼ばれていた技術である。ただ試作や簡単なものだけでなく、現実には産業技術として次の時代の繁栄を支えるところまで発展してきている。レーザーや電子ビームを使って金属粉末や種々の素材を積み重ねて製造し、高い機能性を持たせつつ、軽量で緻密な構造のものを作る。この技術は、航空宇宙や医療などで注目されているし、建設業でも注目され始めたという話も伺っている。
つまり、積み重ねて作るという特徴から、積層造形、Additive Manufacturing(AM)と呼ばれている技術である。実は大阪・関西万博でもこれを食料加工に応用し、筋構造から作成した人工肉が展示されている。本当に実用化されるかは将来を待たねばならないが、食品加工にも大きな発展をもたらす可能性があると思う。
各国政府は、この技術を重視し大きな支援を行っている。数年前には、バイデン政権下のアメリカ政府がAM発展のための政策プロジェクトを初めて打ち出し、アメリカの企業、特に大手企業にはAMで作った製品を積極的に購入することを求めるようになった。ドイツも元々金属AMで先行していたが、さらに近年政府が力を入れ、航空宇宙や医療、そのほかの分野で次々に新製品を開発している。中国も「中国製造2025」の中核技術の一つとしてAMを進めている。習近平主席の掲げる軍民融合政策の下、全ての技術を軍事にも活用する中でAMは重要な鍵となっていると言われる 。
では日本はどうか。今年 4 月に発足した日本AM 学会の関係者の方もこられている。この学会や皆さんの力で現在の日本の課題をどう解決していけるか政府・産業界・大学の出席者にも注目していただき、ぜひ支援していただきたい。
<塾僕武田のコメント>
7月20日に開催する第9回日米デジタルイノベーションハブ会合に、アメリカ最大の政府系シンクタンクであるマイター(MITRE Corp.)の副社長に来ていただく予定であったが2日前のトランプ大統領の日米関税問題の一言で残念ながら取りやめとなった。日本はマイターのようなところと取り組みを進めないといけない。日本での強みが、世界の中で必ずしも通用しないことも考えないといけない。日本には技術の強みがあるとはいえ、これ等は日本だけでやることはできない。
今、最も大事なことは、産官学が連携して国家戦略を描くということである。政府・大学・産業界がそれぞれ独立していては勝てない時代だ。大学の先生に「政策を考えてください」と言っても限界がある。やはり政府と連携して、一つの政策を立てる集団を作っていかなければならない。その中でAMも、今後日本が勝ち残るための基幹産業の一つになると確信している。
そこで大切なことは、日本自から、それを支える基幹産業のOSS自体をどう発展させていくのかということである。OSSについては、単に利用するだけでなく、自ら開発・発展させていくことが必要だ。AIが自ら意識を持つ時代が来るとも言われている。そのときに我々がロボットやAIで培ってきた強みを活かしつつ、長期的な政策を全面的に考える時代が本当に来たと思っている。
<米国の意識の変化について>
私は今、ある種の仮説に取りつかれている。見当違いかもしれないが、トランプ大統領が今やっていることは、「アメリカ式リベラリズムへの反省」ではないかということだ。日本が戦後80年かけて導入してきた米国流の仕組みであるが、米国自身が行き過ぎを感じ始め、変化しようとしているように思える。個人主義の行き過ぎによる社会の分断、行き過ぎた商業主義による富の偏在、さらにはDEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)の推進に伴う新たな軋轢というように、一部の人を優遇し過ぎることで全体に対する問題が出ているという現象への反省が今のアメリカにあるのではないか。日本もその気配が相当でてきつつある。行き過ぎた個人主義の考え方を見直す時期が来ているのかもしれない。