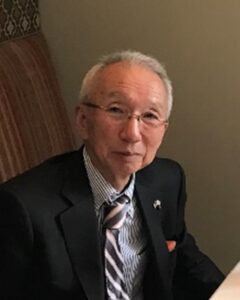<連載>トランプ2.0政権が描く未来への地図 【第8回】トランプの「MAGA」は何を目指すのか ~「MAGA」が目指すのは富永仲基の(異部)加上か?
トランプの「MAGA」は何を目指すのか
「MAGA」が目指すのは富永仲基の(異部)加上か?
トランプ氏が掲げる「MAGA」は、米国式リベラリズムの行き過ぎによる弊害を是正しようとする試みである。「DEI」の見直し、移民制限、対中強硬姿勢、同盟国への負担要求、通商ルールの見直しなどの背景には、リベラリズムがもたらした障害やそれが引き起こした社会の深い分断と中産階級の不満がある。一言付け加えれば、「DEI」の過剰な導入は逆に白人中産階級への差別をもたらしている側面もある。
なお、トランプ政権2.0では政権1.0と異なり、同盟国を「選択的」に扱い、特に英米間の特別な協力関係を強調するなど、冷戦期の普遍主義的同盟観から未来を共にシェアできる同盟への転換を図っている。これは、米国が再び繁栄するための新たな体制を模索する過程ともいえる。
希望的観測かもしれないが、「MAGA」はリベラリズムが掲げた価値を全否定するものではなく、行き過ぎを是正しつつ新たな社会への道を目指すもののように思える。江戸時代の町人学者・富永仲基が「出定後語」で提唱した「(異部)加上説」、すなわち既存の土台に異なる部分を加えることで全く新しい機能を生むという考え方とも重なる。米国式リベラリズムは米国の土台として依然として価値を持つ。その上で「MAGA」が目指すのは行き過ぎを止め、さらに新たな部分を付け加える試みであり、決して強権国家や保護主義国家への逆戻りを意味するものではない。
現下の日本への問いかけ
トランプ政権2.0の5カ月の動きを、単に「高関税主義という無理筋な政策を押し通す政権」と決めつけるのは危険である。米国や英国をはじめとする西欧の一部で起きている大きな潮流を正確に把握しないまま「国益を守る」とするのは、日本が進むべき道を誤るリスクをはらんでいる。
トランプ氏が重視しているのは、彼の支持基盤である共和党支持層と、彼が信頼するごく少数の側近や友人からのアドバイスである。残念ながら、日本政府からの「国益を守る」という声が、これらの層にどれほど届いているかは極めて疑わしい。
英国のスターマー首相は、トランプ氏の立場や支持基盤を理解し、いち早く米国との貿易協定をまとめた。これはトランプ氏の圧力に屈したというよりも、彼が目指す方向を理解し、新たな英国の体制を米国と共に築く意志を示すことで、米国の無用な要求を修正し、英国側、そして世界の利益を確保する戦略的な動きと見るべきだろう。こうしたスターマー氏のアプローチは、トランプ氏やその支持層への有効な働きかけとなり得る点で、日本にとっても示唆的である。
もちろん、これは日本がトランプ氏に従い「DEI」や「LGBT」政策を見直せと言うものではない。また、トランプ氏の圧力に屈する方が良いとも言っていない。ただし、現在のトランプ氏の動きを単なる高関税主義への後戻りと捉えるのではなく、彼が目指す「新たな時代への動き」を冷静に見極める必要がある、ということである。
Big Beautiful 法案
ここまでの議論は、あくまで大きな流れを見たものであり、詳細には不完全な議論となるかもしれないが、あえて現状を参考までにまとめた。日本のメディア(7月2日付)は、現時点でトランプ氏が日米交渉について「合意は疑わしい」とし、自分たちが決める「30%か35%」という数字を日本側に突きつける考えを示したと報じている。もちろん、これは彼特有の「ディール術」である可能性もあるが、日本側が真剣に対応を検討しなければならない別の理由もある。
それは、米国議会上院でトランプ氏が強く推進する「大きなきれいな法案(Big, Beautiful Law)」が可決されたことである。この法案はすでに下院でも可決済みで、今回の上院修正案が可決された後に再び下院に送られ、再可決されれば、トランプ氏が即座に署名し、法律として成立する見通しだ。
この法案には、法人・個人減税の恒久化、インフラ投資、防衛費増額、移民対応への大規模支出が含まれており、成立すれば米国の経済政策は大きく変わる。日本企業や日本市場への影響も避けられないだろう。日米間の協力関係や経済安全保障戦略の再整合が一層求められる。トランプ氏自身、7月4日(米独立記念日)での成立を強く望んでおり、日本側に時間的余裕はあまりない。
ここではこれ以上の議論は控えるが、AI(人工知能)、半導体、DX、宇宙、GXなど、次の時代の繁栄を左右する新興技術(CET)分野において、米国の利益にも資する形でアジア太平洋地域に呼びかけ、新興技術の規制や標準作り、サプライチェーン再編、安全保障技術管理などで具体的な協力を提案し、共に新たな時代に向けたルールを作る姿勢を示すべきであろう。次の時代を共に担う「身内」として、率直に議論し、難題にも逃げずに提案し合える真のパートナーシップを築くことが今こそ重要である。