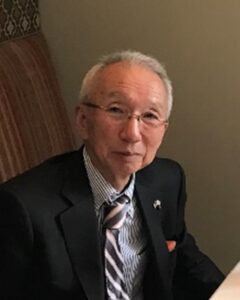<連載>トランプ2.0政権が描く未来への地図 【第7回】トランプ政権2.0の「雷鳴」と世界への衝撃
<雷鳴>
トランプ政権2.0が発足してから早くも5カ月が経過した。この間、「雷鳴」がとどろかない日はなかった。その衝撃は米国内にとどまらず、同盟国を含む全世界にまで及んだ。
内容も多岐にわたり、高関税政策の導入、米国が推進してきたDEI(多様性、公平性、包括性)の否定、政権に反発するハーバードなど名門大学への留学生ビザ発行停止、連邦研究費の停止にまで及ぶ。さらに、ロサンゼルスでの移民政策への抗議デモ鎮圧のため、前例のない米海兵隊派遣を命じた。
また、歴代政権が独立性を尊重してきたFRB(連邦準備制度)のパウェル議長にあからさまな辞任要求を行い、NATO加盟国に対してはGDP比5%への防衛費増額を強く求めた。さらにイランの3カ所の核施設を標的に、7機のB2ステルス爆撃機から地下貫通弾「バンカーバスター」を計14発投下する「ミッドナイト・ハンマー(真夜中の鉄槌)」作戦を実行した。その範囲の広さと強硬さは近年の米政権では例を見ないものである。
<世界は一変>
政権発足前、MAGA派の幹部がワシントン・ポスト紙のインタビューで「発足後には雷の日々が続くだろう」と述べた。この言葉は、単にトランプ政権の未来を占うものではなく、米国民、さらには世界各国とその国民への予告であったといえる。
この「雷鳴」のもとで、米国と世界を取り巻く情勢は一変した。トランプ政権は従来の同盟関係やグローバル貿易の実績を無視し、「MAGA(アメリカを再び偉大に)」を掲げ、一方的に新たな関係を宣言する時代に突入した。世界の国々は、この動きに対し非難し反発する国もあれば、従う国も現れている。
<知識人・メディアからの非難と反発>
こうした動きへの非難や反発は、一部の反米的な政府からも出ているが、より強いのは米国内外のエリート層や主要メディアからのものであろう。
専門家が指摘するその理由の一つは、トランプ大統領の政治スタイル、価値観、表現方法である。西側諸国が重視してきた「理性」、「専門性」、「制度的手続き」と根本的にずれており、さらに「Fake News(偽情報)」、「Shithole countries(くそったれ国)」、「Animal(獣)」など、従来の政治的言語規範を意図的に破壊してきたことにある。こうした言動は、「公共圏の劣化」として批判されるだけでなく、反知性主義的な姿勢や制度・手続きを軽視する態度、さらには他国の内政干渉的な発言を平気で行う姿勢も問題視されている。
しかし、より根本的な非難の理由は、トランプ大統領がMAGA達成を掲げ、米国が第二次大戦後80年かけて築き上げてきた「アメリカ式リベラリズム」を否定しようとしている点にある。
ここでいう米国式リベラリズムとは、「個人の権利と自由を最大化する個人主義」、「政府ではなく市場原理を重視する新自由主義経済」、「国際的な自由貿易と資本移動を推進するグローバル化」、そして「性的マイノリティや移民政策を推進する進歩主義的文化」などを含む体制・文化を指している。 エリートやメディアにとって、トランプ大統領の動きは、西側近代社会が築いてきた政治、知識、経済、文化の基本ルールそのものへの挑戦であり、単なる「間違った政治家」ではなく、「既存秩序の破壊者」として認識されがちである。
<アメリカ式リベラリズムへの根源的な問い>
しかし、こうしたエリートやメディアのトランプ批判とは別に、西側近代社会が築いてきた体制そのものを問い直す声も米国から上がっている。
日経新聞「直言」(6月29日)が紹介した政治学者パトリック・デニーン氏がその代表格である。彼は2018年、トランプ政権1.0の時期に『リベラリズムはなぜ失敗したのか(Why Liberalism Failed)』を出版した。 この著書は、共和党保守派だけでなく民主党リベラル派からも高く評価され、オバマ元大統領ですら「西側社会が感じる意味とコミュニティの喪失を鋭く捉えている」と認めたほどである。
<リベラリズムがもたらした「成功」と「副作用」>
第二次大戦後、米国はこのリベラリズム体制を対抗してきたファシズム(強権・権威主義)や共産主義に代わるものとして国内に導入し、同時に欧州、日本、そして世界へと輸出もした。
戦後の荒廃した欧州や日本は、これを新たな体制のモデルとして受け入れた。中には、憲法を含む法制度、三権分立、経済システムにまでこの理念を組み入れた国もでた。そして、これらの国々は目覚ましい復興と発展を遂げたのである。
そのピークが冷戦勝利後である。いわゆる、「ワシントン・コンセンサス」の名のもと、市場自由化、規制緩和、グローバル化が世界中で推進され、自由主義は最高潮に達した。
しかし、デニーンは、この「成功」をもたらしたアメリカ式リベラリズムも所詮、人間が構築した体制の一つにすぎず、次の体制への踏み台に過ぎないと指摘する。限界を超えて進めば、むしろ失敗を生む体制であると喝破した。
リベラリズムのコアである個人主義は、人間の強みである家族や地域社会との絆を解体させ、市場原理に社会を従属させる結果を招いた。市場経済の行き過ぎは、一部の超富裕層に富を集中させたが、多くの国民は停滞し、格差と分断を深めた。
さらにグローバル化は、製造業の空洞化と雇用流出を招き、米国では金融経済化が進行し、中西部のラストベルト地帯を衰退させ、米国の生産技術力を崩壊させた。また、LGBTや移民問題などの進歩的文化の進行は、米国内の社会的対立を激化させた。
デニーンやその周辺の政治学者によれば、社会の分断をもたらしたのはトランプではなく、彼はこの動きを敏感に察知し、政治的目的のために利用したにすぎないという。また、この進歩的文化が引き起こした深刻な問題は、米国以上に欧州で顕著である。ドイツ、フランス、オーストリア、スウェーデンなどでは移民問題が深刻化し、リベラリズムを掲げた伝統的な中道政党は衰退し、これに対抗する右翼・左翼のポピュリズム勢力が台頭している。これらの動きは、確実に各国の国力を衰退させている。
<日本も直面する「リベラリズムの副作用」>
この問題は日本も例外ではない。日本は当初、選別的にリベラリズムを導入し、高度成長を遂げたが、これが米国との経済的な摩擦を生んだ。1990年代以降は、米国式の金融自由化や規制緩和を本格的に取り入れざるを得なくなり、非正規雇用の増加、地方経済の衰退、実質賃金の停滞を招いた。
この結果、一部利益が上がった大企業はでたが、労働分配率は低下し、地域コミュニティの崩壊が進んだ。さらに、積極的な市場主義の導入が進んだ後は、産業技術力の面で韓国や台湾に迫られ、一部で追い抜かれる結果となった。モノづくり大国の座はこれらの国に移行しつつある。
結果として、日本の中産階級も米国と同様の変化を経験しつつある。シンガポールや香港に一人当たりGDPで抜かれ、かつての「圧倒的リード」は失われつつある。彼らが国家主導や家族経営を一定程度維持し、リベラリズムの悪弊を完全には受け入れていない点は示唆的である。
日本の相対的地位低下は、単なる競争力の問題ではなく、戦後西側モデルを無批判に追随した結果ともいえる。個人主義や進歩的社会文化をどれほど導入しても、それだけでは抜本的な解決にはつながらない。日本版のMAGAともいうべき「MJGA(日本を再び偉大な国にする)」を真剣に模索すべき時期に来ているようである。