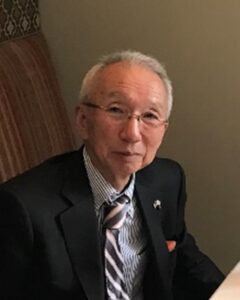【データ基盤から知識基盤へ】第72回無名塾(3月18日開催) 講師:黒橋 禎夫氏 (国立情報学研究所(NII)所長/京都大学 特定教授)
<塾僕武田のコメント>
国立情報学研究所所長(http://researchmap.jp/kurohashi/)で自然言語処理研究の第一人者である黒橋禎夫先生に話題を提供して頂く。先生の研究は一見難解に思えるかもしれないが、その成果は私たちの生活に深く浸透している生成AI(Generative AI)として実を結んでいる。この延長線上には、人間の知能に匹敵する「汎用人工知能(AGI)」の到来が見据えられているが、現在、米国や中国をはじめとする各国が熾烈な開発競争を繰り広げている分野である。
記憶に新しいかもしれないが、トランプ大統領は今年1月21日、就任式の翌日にホワイトハウスで記者会見を開き、OpenAI、ソフトバンクやオラクルのトップが同席する中で、数十兆円の予算を投入し、政府と民間が一体となりAGI開発を目指す「スターゲート計画」を発表した。このニュースはメディアでも大きく取り上げられ、米国のAI戦略で主導権を握ろうとする姿勢が鮮明になった。
これとほぼ同じタイミングで、さらに衝撃的な出来事があった。中国の新興AI企業DeepSeekの創業者、梁文鋒(リヤン・ウェン・フォンLiang Wenfeng)による中国版の生成AIモデル「DeepSeek」の発表である。このニュースは、スターゲート計画ほど大きく取り上げられなかったが、AIの専門家の間で大きな衝撃が走った。彼らはそれまで、「中国は生成AIの分野で出遅れており、また、Nvidiaの最先端チップなしで、米国に追いつくことは不可能」と考えていたからである。しかし、DeepSeekによって、この認識が完全に覆された。
リャンは、OpenAIの開発コストの数分の一という低コストで、最先端のチップを使わずに同等の性能を実現したのである。これについて、オックスフォード大学の経済学者ダニエル・サスキンド(Daniel Susskind)は、2月1日付の『タイムズ』紙で、「A Sputnik Moment(スプートニクの瞬間)」と評した。 これは1957年、ソ連が世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功したことで、西側諸国が『自分たちは技術的に遅れをとった』と恐怖した瞬間と捉えられたが、サスキンドは、DeepSeekの出現が同様の衝撃をもたらしたと指摘している。 事実、この後にリャンは、「DeepSeek-V3」や「DeepSeek-R1」という、OpenAIやMetaの最新のモデルに匹敵するプログラムを発表している。
世界のAI市場の競争の力学が一変しかねない事態を受けて米国政府は対抗策の検討を開始した。 DeepSeekを単なる技術的な成功と捉えるだけでなく、地政学的な影響も大きい。中国の経済・軍事・安全保障の強化に直結し、ひいては民主主義体制への脅威となる可能性がある。
この熾烈なAI開発競争の中で、日本が直面する課題は何か。特に日本政府が取るべき戦略や人材育成のあり方について、黒橋先生にお話を伺いたい。 この答えは一挙にはでてこないが、皆さんがその答えを探るきっかけとなれば幸いである。