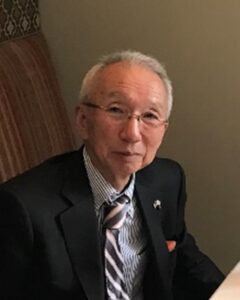<連載>トランプ2.0政権が描く未来への地図 【第3回】トランプ2.0政権の前評判 「サンダーの日々」とは
<雷の日々>
トランプ2.0政権の科学技術政策を見ていく前に、その発足に関する現状を整理しておきたい。ワシントンポスト紙によれば、トランプ1.0政権の戦略を担っていたスティーブ・バノンは、トランプ2.0の展開を映画『デイズ・オブ・サンダー(雷の日々)』になぞらえて「雷の日々」と呼んでいるという。 この映画は、1990年に公開されたトム・クルーズ主演によるカーレースの映画で、彼が演じる若きレーサーが事故やライバルとの衝突を乗り越え、最終的に「デイトナ500」で優勝する物語である。バノンがこの映画を引用したのは、トランプ2.0が激しい対立を繰り返しながらも最終的に勝利を目指す姿を表現しているのだろう。
<トランプ大統領の発言と国際社会の反応>
バノンの予想通り、トランプ大統領はすでに挑発的な発言を繰り返している。例えば、
- グリーンランドの買収に言及
- パナマ運河の支配権の取得
- カナダ・メキシコ・中国への追加関税
- 「メキシコ湾」の名称を「アメリカ湾」に変更
- ネタニヤフ・イスラエル首相との会見で「米国がガザを所有」との発言
これらの発言は、世界中で大きな反発を招いている。
<閣僚承認の難航と政権内部の亀裂>
トランプ政権の新たな閣僚人事も「雷の日々」が続いている。上院の承認プロセスでは、就任式当日にマルコ・ルビオ氏の国務長官任命は全会一致で承認されたものの、これは例外であった。国防長官候補のピート・ヘグセスは、過去のスキャンダルや経験不足が問題視され、上院の投票は50対50の同数となり、JD・ヴァンス副大統領が決定票を投じる事態となった。まだまだ問題となる閣僚候補が多く続いている。また、閣僚候補以外にも上院の承認が必要な政府上級職員は1,200名にも及ぶため、トランプ2.0が完全に軌道に乗るまでには、「雷の日々」が続くであろう。
さらに、政権内部での対立も激化している。バノンは、新たに政権に加わったイーロン・マスクについて「邪悪で、南アフリカに帰るべきだ」と非難。一方のマスクも、バノンらを「低能で危険な意地の悪い連中」と呼び、公然と批判している。このような内部対立は、トランプ2.0の行方をより不透明にしている。
<トランプ2.0の支持率と評価>
こうした混乱が続く中、トランプ2.0の支持率は一定の安定を保っている。英エコノミスト/YouGovの世論調査によれば、
- 共和党員の94%がトランプ大統領を支持(2017年は81%)
- 就任演説を「優れたもの、または平均以上」と評価した人は62%(2017年は49%)
- トランプを「強い指導者」と考える米国人は43%(就任当初は32%)
特に共和党支持層では、トランプ大統領の関税政策や「アメリカ第一」政策が根強い支持を集めている。たとえば、PEW ResearchやGallupの調査によると、共和党員の4人に3人、民主党員の半数が、米国は貿易で得るものより、失う方が大きいと考えている。つまり、アメリカ人(民主党員・独立系もあわせて)は、貿易が消費者の選択肢を広げたと考えるが、自分たちの雇用と賃金は損なわれたと考えている。また、関税ではアメリカ企業の48%と労働者の43%は自分たちを保護するための関税を支持している。そして、アメリカ人の3分の2が関税により物価が上昇すると信じているが、共和党員の半数がそれに同意していない。これら共和党員は、関税政策がもたらすインフレと失業の双子の結果を心配していないことになる。このような中で、「アメリカ第一政策」が進むと考えられる。
<米国の国際的地位への影響>
トランプ大統領は、就任演説で「アメリカは再び繁栄し、世界から尊敬される国になる」と述べた。しかし、国際社会の評価ではアメリカ人の中でも分かれている。先の英エコノミスト/YouGovの調査では、
- 4年後にアメリカの尊敬が高まると考える人:40%
- 低下すると考える人:38%
これは2017年時点の調査(高まる31%、低下する41%)と比較すると改善が見られるものの、依然として意見は二分されている。
<IR理論から見るトランプ2.0政策>
ハーバード大学の国際関係論(IR)教授スティーブン・M・ウォルトは、トランプ2.0の国際的影響をIRの3つの理論のリアリズム(現実主義:国際関係を権力闘争や国家利益の観点から分析する理論)、リベラリズム(自由主義:国家間の相互依存や国際協調を重視し、国際機関や国際法の役割を強調する理論)、コンストラクティビズム(構成主義:国際関係が社会的に構築されたものであり、アイデンティティや規範、文化などの非物質的要因が国家の行動に影響を与えるとする理論)を使って分析した。
興味ある人に付け加えると、リベラリズムの代表的な学者にはジョセフ・ナイ、リアリズムにはハンス・モーゲンソー、あるいはコンストラクティビズムには「アナーキーは国家が作り出すもの」という論文で知られているアレクサンダー・ウェントがいる。以下の図はウォルトの分析の結果である。
| IR理論 | トランプ外交の特徴 | 予測される影響 |
| リアリズム | 力を重視し、経済制裁・軍事力を活用 | 多極化の加速、米国の影響力低下 |
| リベラリズム | 国際機関の軽視、協調の否定 | 国際ガバナンスの崩壊、貿易の分断 |
| コンストラクティビズム | 「アメリカ第一主義」、信頼の低下 | 米国のソフトパワー喪失、同盟国の自立 |
いずれも、ウォルトの分析では、トランプ2.0は短期的には一部の譲歩を引き出すかもしれないが、長期的には国際社会の反発を招き、友好国を失い、敵対国を増やし、影響力を低下させるリスクがある、としている。
<「サンダーの日々」は続く>
トム・クルーズは、昨年11月に『デイズ・オブ・サンダー2』の制作に向けてパラマウント・ピクチャーズと交渉中との報道があった。果たして、続編が実現し、困難を克服して勝利を収める物語となるのかは不明である。同様に、トランプ2.0が最終的に成功を収めるかどうかも不透明だ。しかし、一つ確かなのは「雷の日々」が続くこと、そして、「アメリカは再び繁栄し、世界から尊敬される国になる」のは、2.0の科学技術政策が要となり、最大の要因になることである。 (代表武田 記)